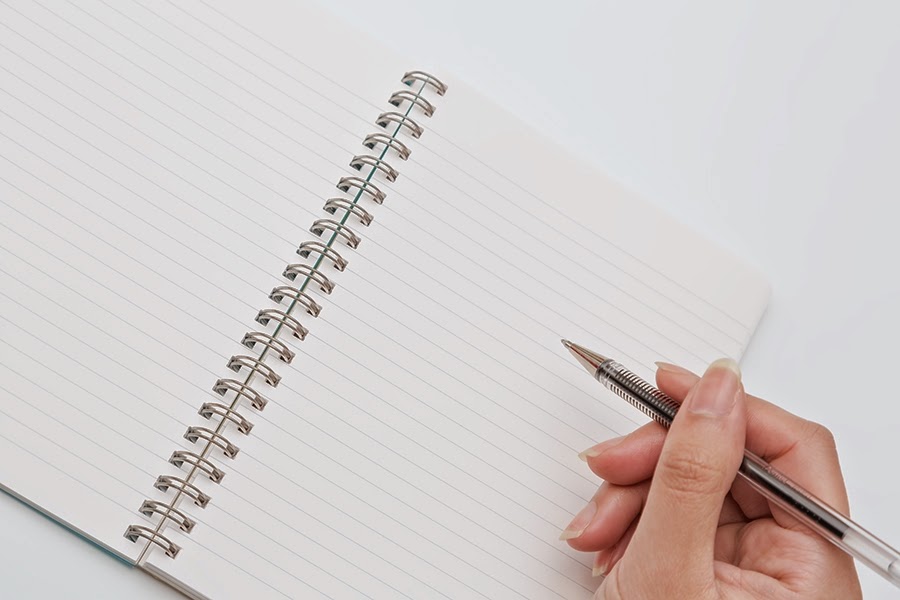平成24年4月1日の診療報酬改定以降、ジェネリックが存在する医薬品を一般的名称に剤形及び含量を付加した記載にかえて処方せんを交付した場合に医療機関は一般名処方加算を算定できるようになった。
ちなみに、
「一般的名称に剤形及び含量を付加した記載にかえた処方」のことを一般名処方と呼ぶ。
名称を変更して処方箋を交付するだけで一般名処方加算:2点がもらえるもんだから、
平成24年4月1日をさかいに急激に一般名処方が普及した。
普及し始めたら頃は、
一般名の医薬品の書き方が、統一されていなかったがいまはどこの処方箋も同じような記載で統一されている。
おそらく、レセコン会社側が改善して訂正してくれたのだろう。
先日、厚生労働省が、
処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成26年12月12日適用)というのを発表したことからも、
ほとんどの医療機関が一般名処方マスタ通りの記載となっている。
一般名処方の正式な書き方
原則
最初は、この【般】がなかったりしたんだけど今は大体ついてますね。
この【般】がないと薬剤師なら一般名処方ってわかるだろうけど、事務は判断することができません。
表示が義務というわけではなさそうですが、ほとんどのレセコン会社がこの表記に対応したので、いまはほとんど入ってます。
「一般的名称」ってのは添付文書に書いてある有効成分の一般的名称を基本にするんだけど、これだと長すぎてややこしくなってしまう。
だから、これをもとに既収載品の販売名も参考にして一部簡略化したものもあります。
例)
アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン
ジクロフェナクナトリウム → ジクロフェナクNa
ロキソプロフェンナトリウム水和物 → ロキソプロフェンNa
配合剤については、原則として、有効成分の一般的名称(原則として、塩及び水和物に関する記載は省略)を「・」で接続し、含量は記載しないこととしていますが、同一の有効成分を含有し、含量のみが異なる複数の製剤が存在するときは、区別のため、一般的名称の後に含量を記載しています。
例)
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
その他、同一の有効成分・剤形を有する医薬品であって、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合には、括弧書き等により区別を行っているものがあります。
例)
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)
【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)
医薬品名・規格・剤形が同じで区別がつかないから()で更に条件を加えるんです。
温湿布と冷湿布は規格や剤形で区別しきれないから特別に(温感)(非温感)で区別します。
またアダラートにはCRとLがあるしどちらも徐放錠だから効き目の時間を()に記載して区別します。
細かく規定されているが、それでもまだ例外は出てくる。それが総合感冒薬などの3種類以上の色々な成分が入っている薬です。
これは困ります。すべての成分を表示するとすごく長くなってしまいますからね。
では、有名なPL顆粒で見てみましょう。
PL顆粒の一般名は【般】非ピリン系感冒剤(4)顆粒です。ずいぶん簡略化されましたね。
もうちょっと例を見てみましょう。
例)
フスコデ錠→【般】鎮咳配合剤(1)錠
カフコデ錠→【般】ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤錠(2)
ピーエイ錠→【般】非ピリン系感冒剤(4)錠
ビオフェルミン錠→【般】ビフィズス菌製剤錠
ビオフェルミン散→【般】ラクトミン散(1)
こんな感じです。
ラクトミン散とか最初はびっくりしましたが入力してみたらビオフェルミンだったのでいつもの薬だったなんてことはよくある。
一般名処方を調剤するときの注意点
一般名処方できたときは先発後発にかかわらず、だした内容のものを医師にあとで知らせなければならない。
FAXでもTELでもいいんだけど、
これって薬局の負担も、病院の負担も相当なものでよね。
だから、事前にこの一般名のときは「この薬で渡す」と取り決めを行うことでこの連絡を省略ができる。
ほとんどの処方箋は門前薬局に流れていくので連絡は少なくて済むわけだ。
初めての医療機関の処方箋が一般名だったときは連絡しないとダメですね。
一般名処方の変更調剤ルール
一般名 → 先発品はOK
一般名 → 後発品もOK
一般名5mg → 後発品2.5mg×2TでOK
一般名5mg → 先発品2.5mg×2TはNG
一般名口腔内崩壊錠 → 後発品なら普通錠でOK、カプセルでもOK
一般名口腔内崩壊錠 → 先発品なら普通錠はNG、カプセルもNG
つまり後発品で出すなら規格を変更してもいいし、剤形も変更していい。
先発品で出すなら規格変更も剤形変更も不可。
ほんと融通が効かないのだ。
一般名処方を先発品で出した時には理由をレセプトに記載しなければならない
タイトルのとおりなんだけど、
一般名できた処方箋を先発品で出した時はレセプトに先発でだした理由を記載しなければならない。
簡単なアンケートみたいなもんで、
「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」、「その他」
この4つの中から選べばいい。
これらを処方箋を入力している時に選ぶので事務員の仕事です。
患者にジェネリックの意向をきいて入力するわけだ。
ジェネリックを在庫しているときは、患者の意向をきいて先発がいいというなら「患者の意向」、在庫してない時は無条件で「保険薬局の備蓄」 です。
てか、「その他」は思い浮かばないし、「後発医薬品なし」も意味がわからない。「後発医薬品なし」のものが一般名でくるのか?って根本的な疑問がある。
だから、実質的につかうのは 「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」この2パターンだけだ。